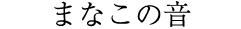一 幻のけやきを探せ
時は天武天皇の御代。
「ただひとつの、類い稀なる厨子を作りたい」
そんな朝廷の声が都中に広がると、腕に覚えのある職人たちの間には熱い視線が交わされた。
その中のひとり、木工師の茂丸(しげまる)は、
どうやら山奥に“玉杢(たまもく)のけやき”があるという噂を耳にする。
「玉杢ってのは、木目が玉のように浮かぶ珍しい模様らしい。
もしそんな材を手に入れられたら、朝廷の度肝を抜ける傑作が作れるぞ」
茂丸は目を輝かせ、意気込む。
周囲は「絵空事じゃないのか」と半信半疑だったが、彼は意に介さず山へ踏み出した。
何日も奥深い谷をさまよった末、たどり着いたのは、巨躯のけやき。
いかにも年輪を重ねた風格に、幹にはちらりと浮き上がる不思議な杢目。
「こいつはただものじゃねぇ…」と茂丸は熱い息をつく。
二 命がけの伐採と運搬
しかし、木を見つけたからといって安堵はできない。
「この急斜面でどうやって安全に倒す?」「下手をすれば大惨事だぞ!」
仲間はみな戸惑うが、茂丸は冷静に木の傾きを見定め、鋸(のこぎり)を入れていく。
バキバキ…ゴォン! 大地を揺るがす音とともに、けやきが倒れた。
切り口から覗く玉杢は、波打つように光をはらんでいる。
「すげえ…」と誰かが呟いたきり、しばし言葉がない。
だが、ここからが本当の試練だ。
巨大なけやきを京までどうやって運ぶのか。
滑車や丸太を使い、綱を何重にも巻き付け、
崖ぎわでは全員が必死の形相で声を掛け合う。
雨が降ればぬかるみに足をとられ、晴れればじりじりと体力を削られる。
「このけやきを陛下に見せられなきゃ、俺たちの苦労は水の泡だ!」
そんな一念で、なんとか京の町まで辿り着いた。
三 粋な職人魂
工房の中央に据えられたけやきは、まるで山の神が宿るかのような迫力を放つ。
茂丸は静かに息をつき、「ここからが俺たちの本領発揮だな」と心を引き締める。
当時の道具は鑿(のみ)、槌(つち)、鋸(のこぎり)程度。電動工具などあるはずもない。
茂丸は一刀ごとに木の癖を読み、玉杢の魅力を最大限に引き出そうと神経を尖らせる。
「ちょっとでも削りすぎたら台無しだ…」
真夜中まで灯をともしては「あと髪の毛一本分だけ…」と微調整を繰り返す。
仲間から「倒れるぞ」と制されても、「今は夢中で寝てなんかいられない」
と意気込む茂丸。木の肌を撫でるその目は真剣だ。
四 天皇へのお目見え
そうして完成した厨子は、まばゆいほどの艶をたたえていた。
漆を重ね、金具を打ち、玉杢の文様がふわりと揺らめく。
いよいよ朝廷へ献上する日がやってきた。
王宮の広間、布が静かに取り払われると、人々は思わず声を呑む。
天武天皇は一歩前へ進み、厨房(くりや)のように澄んだ目で見つめる。
「これは見事だ…自然が描いた美と、人の技が溶け合っている」
その言葉に、茂丸は熱い息を吐きだす。
「ようやく、思いが届いたんだ…」と胸をなで下ろした。
五 歴代へ受け継がれる厨子
こうして玉杢の厨子は献上され、
持統天皇、文武天皇、元正天皇、聖武天皇、孝謙天皇へと順々に受け継がれていく。
聖武天皇のときには「宝物倉に仕舞い込んでいては惜しい。
祭礼の場で披露して、人々がその美を目にするべきだ」
とのお達しがあったとか。
孝謙天皇は「この玉杢の文様は、玉の滴りのようだ」と感嘆し、“天皇の慈愛の品”と呼んで大切にしたという。
六 時を超えてなお
あれほど情熱を燃やした茂丸たちも、けやきを倒す手助けをした男たちも、
今や誰ひとりこの世にいない。
切り口から立ち上る匂いも、夜通し削り続けたときの息づかいも、
遠い昔に失われてしまった。
それでも、この厨子を前にすると、昔の人々の想いがふっと胸をよぎる
そんな声が、今もどこかで囁かれているだろうか。
歴史の上を流れる大きな時間のなかで、人の営みは儚く消えていく。
それでも、この厨子を眼にしたとき、かつてそこにいた名もなき職人や、
山の奥で生きていたけやきの面影が、微かにゆらりと揺れ動くようだ。
ひとつの作品が長い年月を旅しながら、いくつもの想いを帯び続ける
その静かな輝きこそが、茂丸たちの心が今も息づいている証かもしれない。